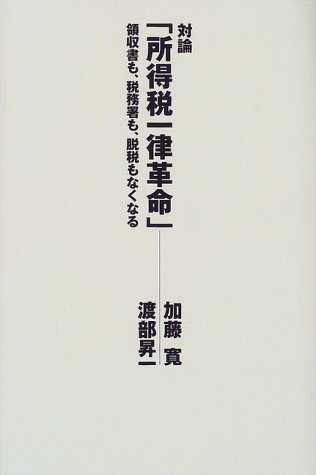・『知的生活の方法』渡部昇一
・『続 知的生活の方法』渡部昇一
・大村大次郎
・『消費税は民意を問うべし 自主課税なき処にデモクラシーなし』小室直樹
・『税高くして民滅び、国亡ぶ』渡部昇一
・日本を凋落させた宮沢喜一
・私的所有権を犯した国家は滅ぶ
・貧富の差がないところは住みにくい
・規制緩和が税金を安くする
・「法」と「立法」を峻別する
・大蔵省の贋金(にせがね)づくり
・裁量権を認めるところに法の支配はない
・主税局の見解「所得税は7%で十分」
・『封印の昭和史 [戦後五〇年]自虐の終焉』小室直樹、渡部昇一
・『新世紀への英知 われわれは、何を考え何をなすべきか』渡部昇一、谷沢永一、小室直樹
・『消費税減税ニッポン復活論』藤井聡、森井じゅん
私はかつて大蔵省の政府税制調査会委員に任命されていたことがあります。そのころのことですが、昭和5年生まれの竹村健一氏とか日下公人(くさかきみんど)氏とか鎌倉節(かまくらさだめ)氏などと初午会(はつうまかい)という親睦会をつくって時折話し合っていました。その我々5~6人の集まりに、主税局長がわざわざ挨拶に来られて、要するに消費税を通してもらいたい、よろしく消費税の重要性を説いてほしい、と腰を低くして頼みにみえられた。そのとき私は、
「ハイエクさんは所得税は1割前後でいいとおっしゃっていたけれど、主税当局はどうお考えですか」
とイヤな質問ですがやってみた。
主税局長はいまの日本たばこ産業社長・水野勝(みずのまさる)さんでした。彼はそういういやらしい質問に対して、アーとか、ウーとか、エーとか、それはとか言わないで、
「国民の皆さんに納めていただければ、10パーセントは要りません。7パーセントで結構でございます」
と答えてくれました。私はいまでも水野さんを尊敬していますが、あの躊躇なき明確な返答には感心しました。(渡部昇一)【『対論「所得税一律革命」 領収書も、税務署も、脱税もなくなる』加藤寛〈かとう・ひろし〉、渡部昇一〈わたなべ・しょういち〉(光文社、1999年)以下同】
・一律一割の税金で財政は回せる/『税高くして民滅び、国亡ぶ』渡部昇一
「大蔵官僚の発言は1960~70年代だろう」と書いたが間違っていた。水野が大蔵省主税局長を務めたのは1985-88年である。バブル景気(1986-91年)の真っ只中だ。するってえと、どうなんだろうね? 所得税を払っていない連中が多いのか? あるいは所得を誤魔化しているのか? わからん。ブラックマネー以外で所得税を回避することは難しいだろう。
そもそもいまのサラリーマンが払っている所得税というものは、真の意味では所得税とはいえないもので、じつは企業が国に支払っっている雇用税でしかないのです。所得税というものは、所得を得た人がその所得に応じた税金を払うことですが、サラリーマンは誰もが自分では支払っていない。いや、会社が代行してくれていると言いますが、では代行依頼契約を正式に取り交わしているかというと、そんなことはしていない。だいたい、自分の所得税がいくらなのか即座に答えられる人はきわめて少ないのです。
竹内靖雄(たけうちやすお)成蹊大学教授が『正義と嫉妬の経済学』(講談社)の中で、サラリーマンが給料から所得税を払っていると考えるのはフィクションだ、と指摘しています。税金というのは手にした収入から自分が政府に納めるものですが、サラリーマンは手取りいくらかの金額をもらっているだけです。ゆえに、理論的には、企業がその従業員の賃金に見合って課せられている「雇用税」ということになる。サラリーマンは一人一人が払っているのではなく、企業が払っているのだから、企業雇用税ということです。
税金というものを定義するならば、節税や脱税をしうるものが税金ということになります。しかし源泉徴収された後の給料だけを手にするのですから節税も脱税もしようがない。はじめから脱税のできないようなものは税金ではない。したがって源泉徴収される税金は個人の税金ではなく雇用税ということになります。
どうしてこんなシステムになっているかを考えると、徴税の一大原則である「税金は取りやすいところから取りやすい形で取る」――を大蔵省が実行しているためです。(渡部昇一)
竹内靖雄の著書は読んだ。面白かった記憶はあるが所得税の指摘は全く覚えていない。私の興味が税に向っていなかったためか。
国民の政治意識を向上させるためにも源泉徴収はやめた方がいい。納税の手続きを会社にやらせるのもおかしな話だ。一億総確定申告で構わない。